 Audio
Audio for SMiLE lab FSL-SH1000
フォースマイルラボのカートリッジキーパー「FSL-SH1000」を入手しました。カートリッジがだいぶ増えてきて、それぞれ元々付属のケースに収納してクローゼットにしまってあったのですが、それだとどうしても交換するのが億劫になってしまいがちでし...
 Audio
Audio  Audio
Audio 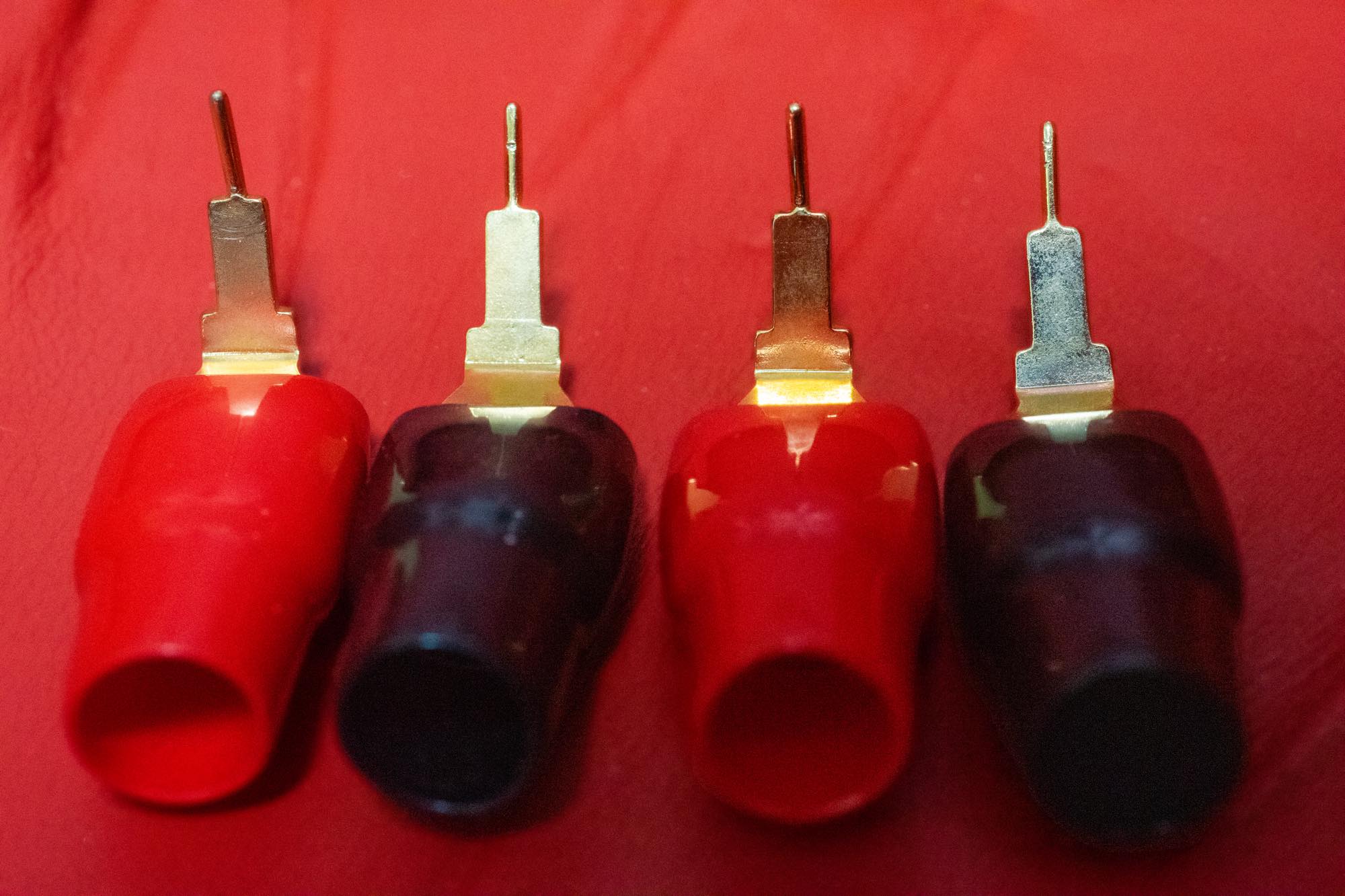 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio 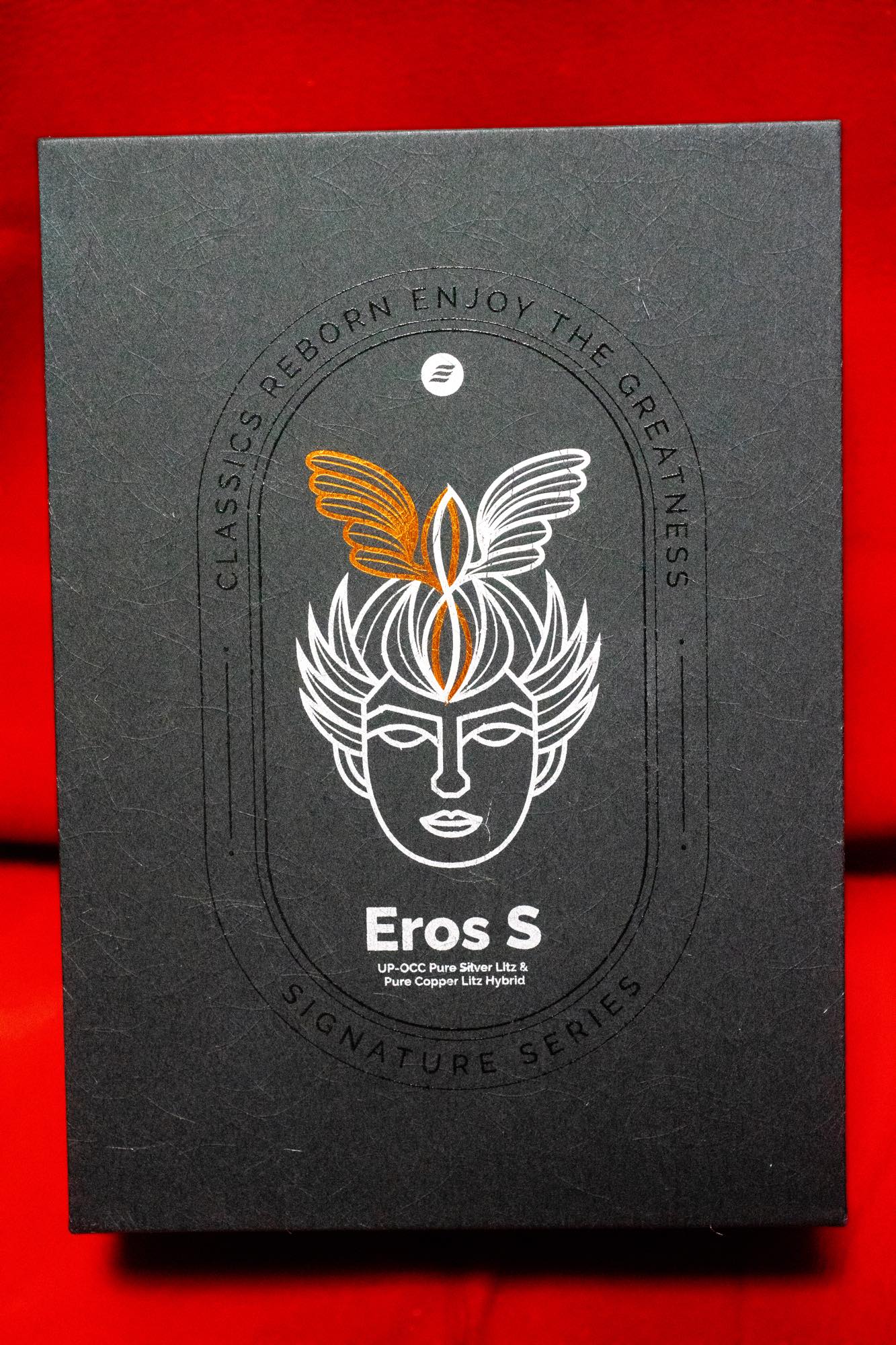 Audio
Audio 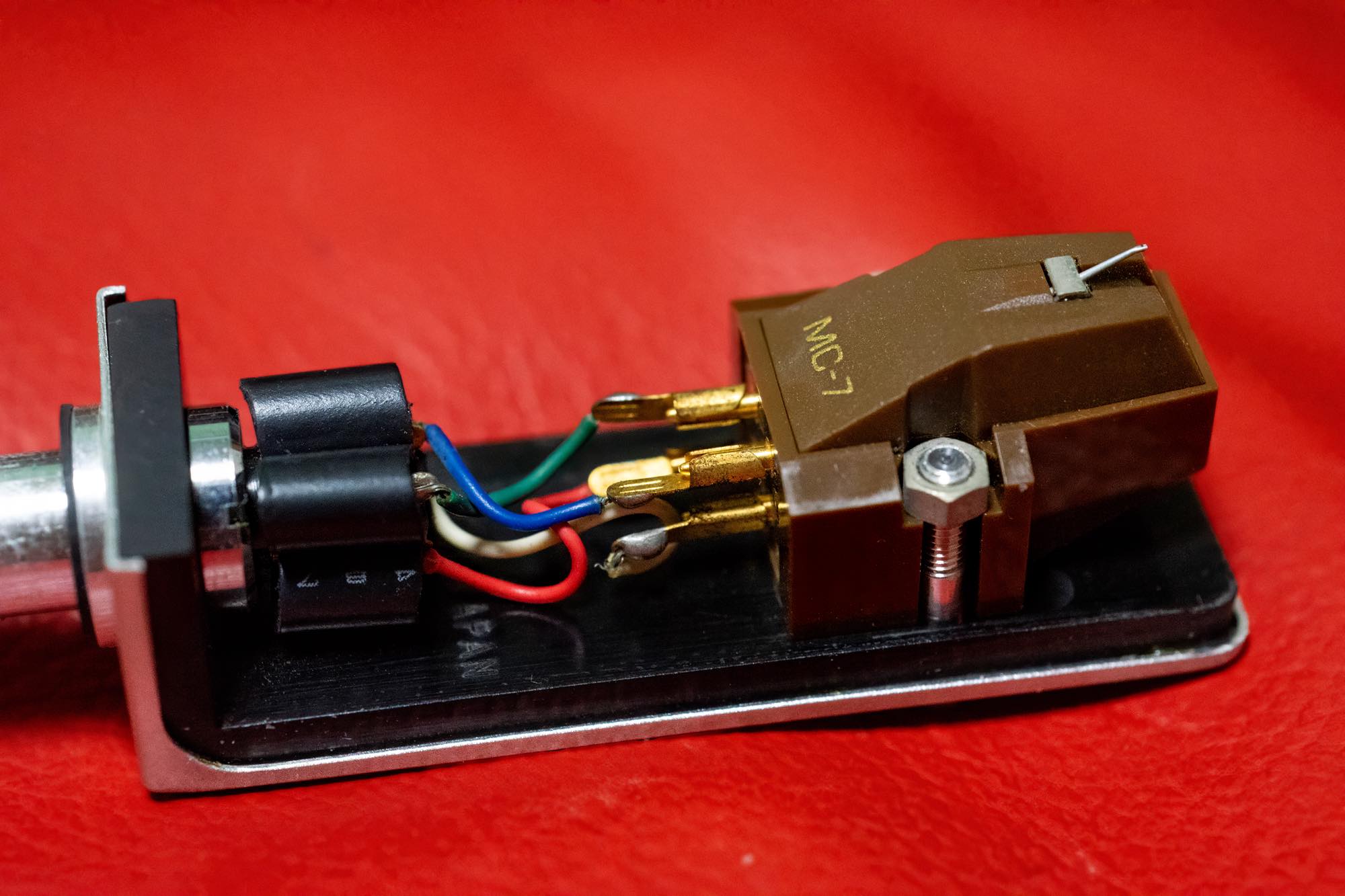 Audio
Audio  Audio
Audio