 Audio
Audio TEAC X-10R
TEACのオープンリールデッキ「X-10R」を入手しました。以前から10号リールテープ、そして先日は7号テープを入手していたので、いつかデッキが欲しいなと狙っていたんです。ずいぶん昔にTEAC X-3(mkIIだったかも)を持っていて、せっ...
 Audio
Audio  Audio
Audio 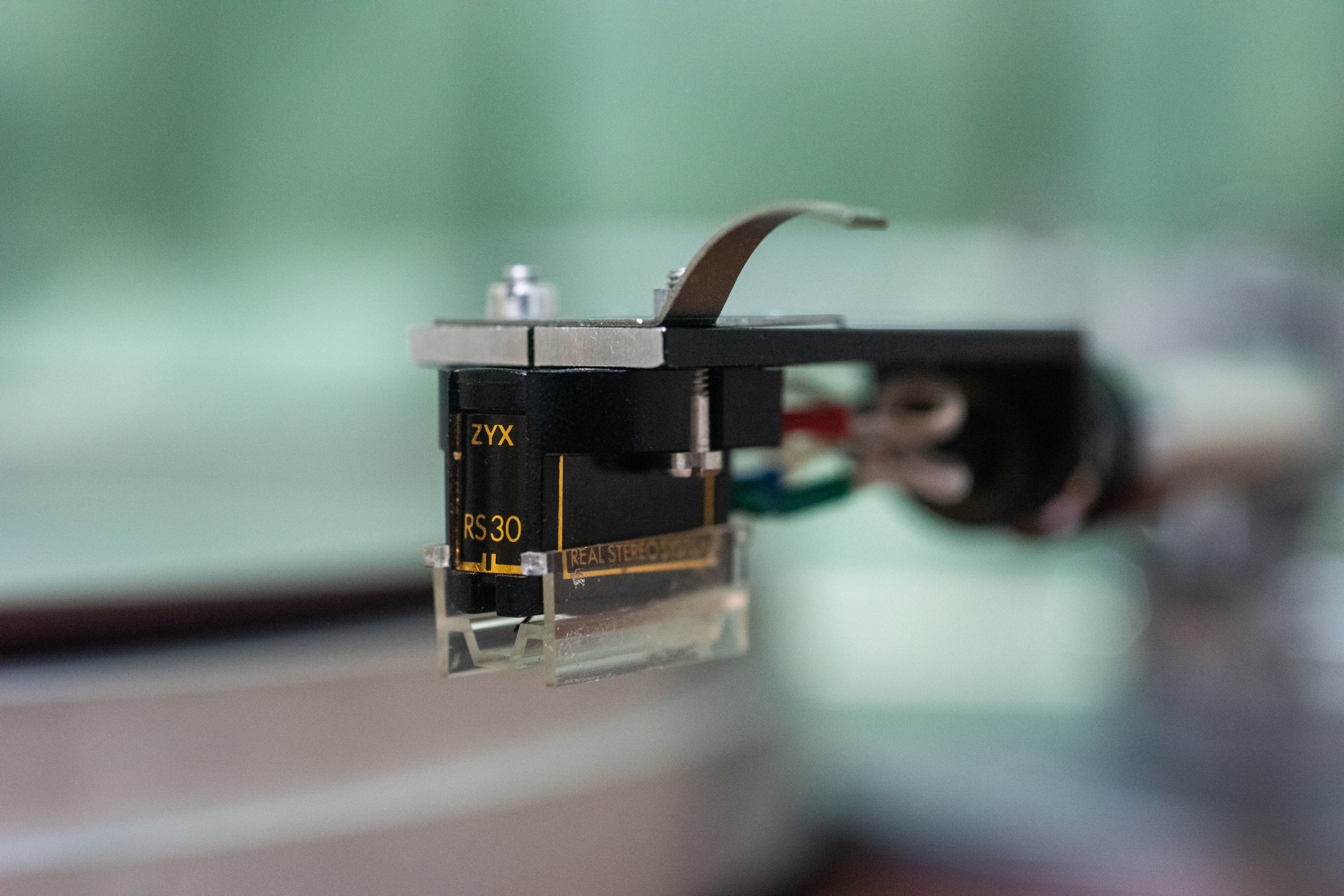 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio 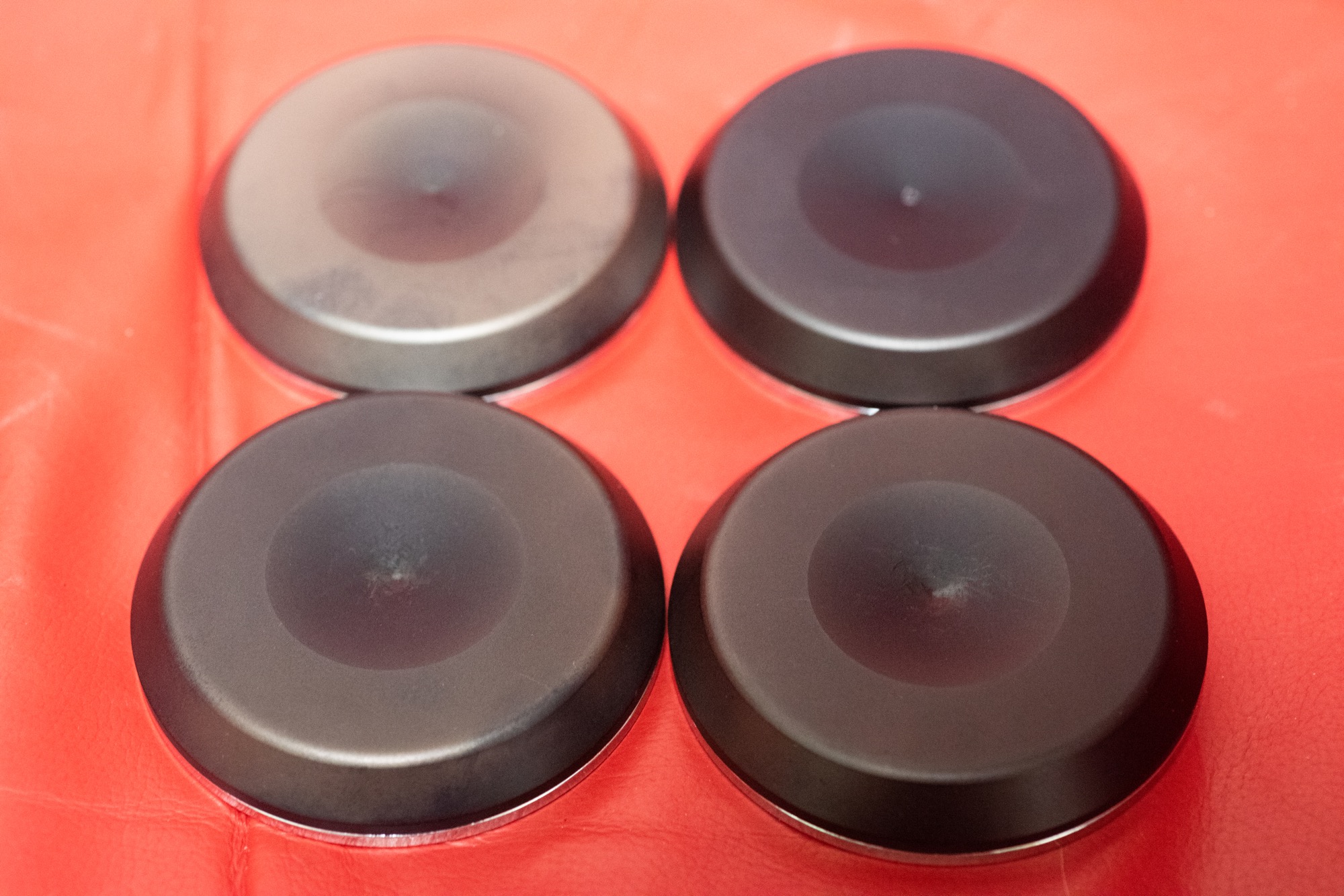 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio