 DigitalPhoto
DigitalPhoto SONY SEL50M28
SONYのマクロレンズ「FE 50mm F2.8 MACRO」を入手しました。α7、α7IIと使っていますが実はまだEマウントの35mmフルサイズ対応レンズを持ってなかったんですよね。その前のNEXからの資産としてAPS-Cのはあったんです...
 DigitalPhoto
DigitalPhoto  Audio
Audio  Audio
Audio  Mac
Mac 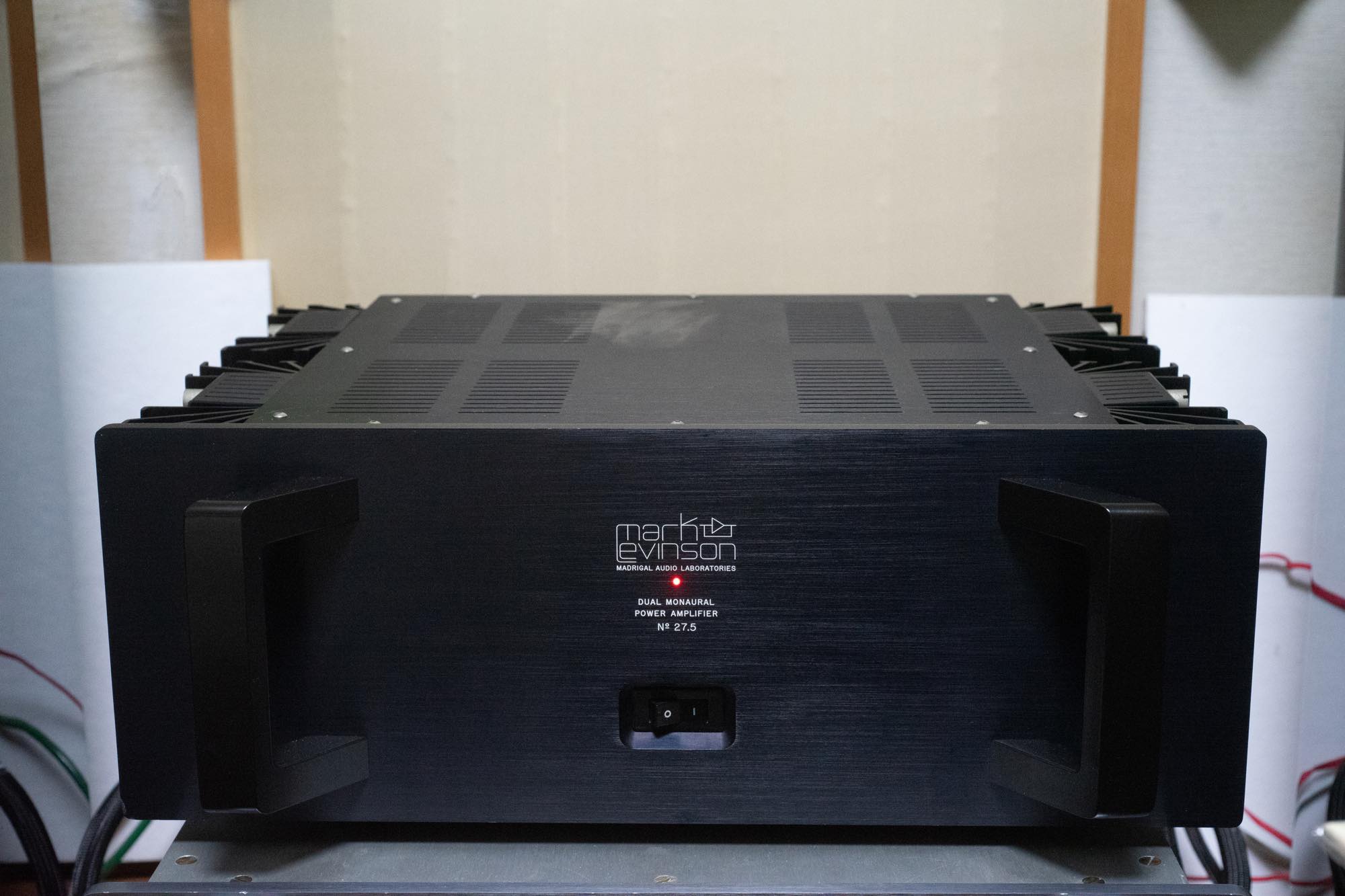 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio 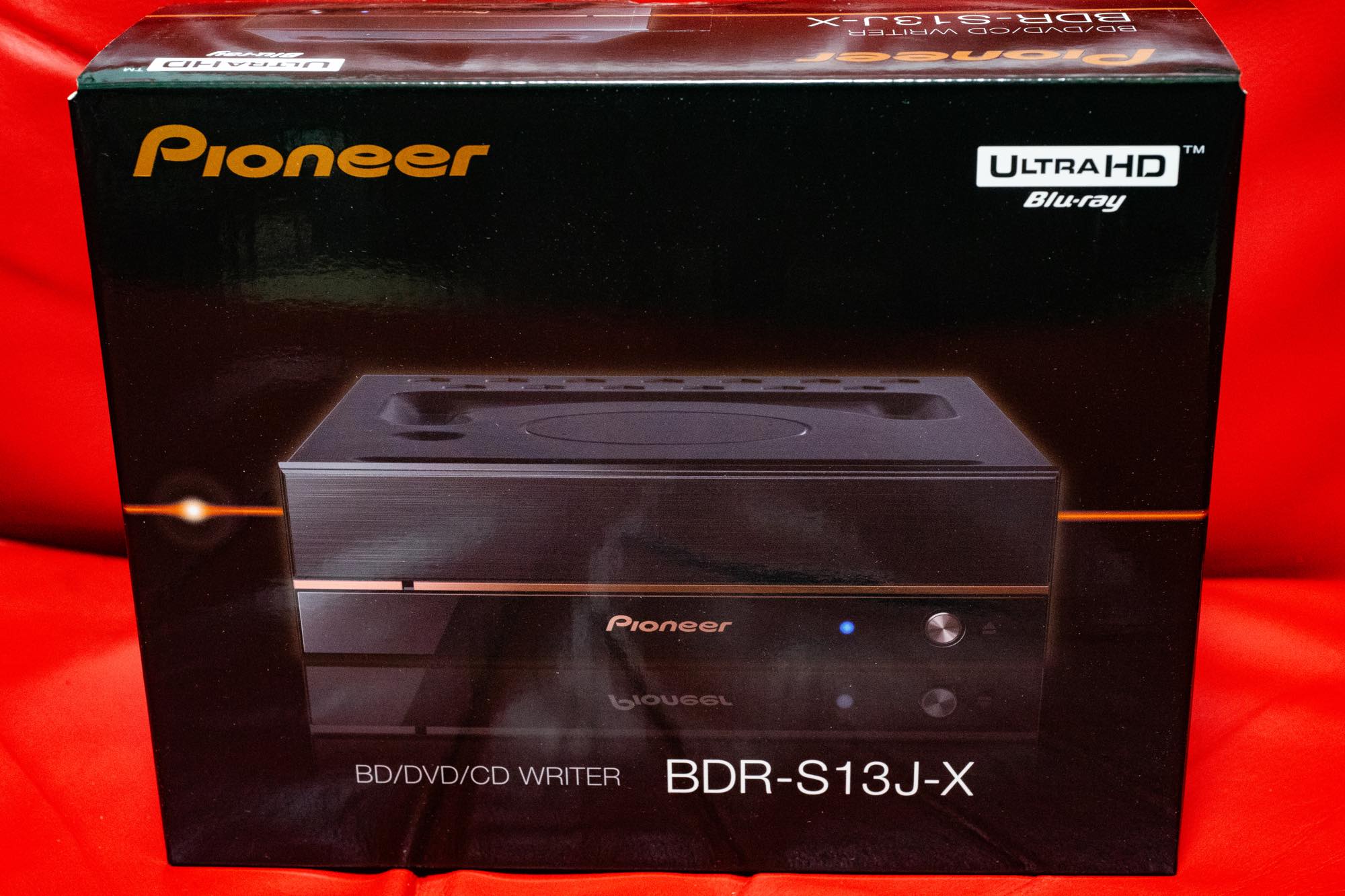 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio