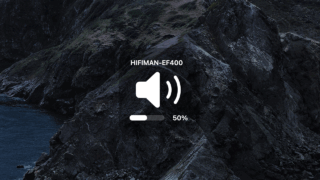 Mac
Mac MuteHUD 1.2
ミュートとボリュームのHUD表示ユーティリティ「MuteHUD」を1.2にアップデートしました。1.1でボリューム表示に対応しましたが、今回は出力デバイス名をHUDの上側に表示するオプションを追加しました。デフォルトはオフにしてありますので...
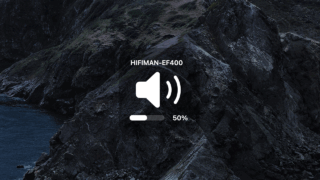 Mac
Mac  Mac
Mac  Audio
Audio 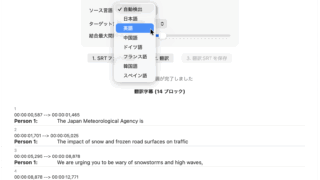 Mac
Mac  Mac
Mac  Mac
Mac  Mac
Mac  Mac
Mac  Photo
Photo  Mac
Mac