 Audio
Audio KRELL PAM-3 レビュー 到着編
先日のKSA-100につづいて、KRELLのプリアンプ「PAM-3」を入手しました。10年くらい前に再開したオーディオですが、Accuphase主体に乗り換えてから音楽自体はあまり楽しくない状態が続いていて、少しそこから脱却したいなというの...
 Audio
Audio 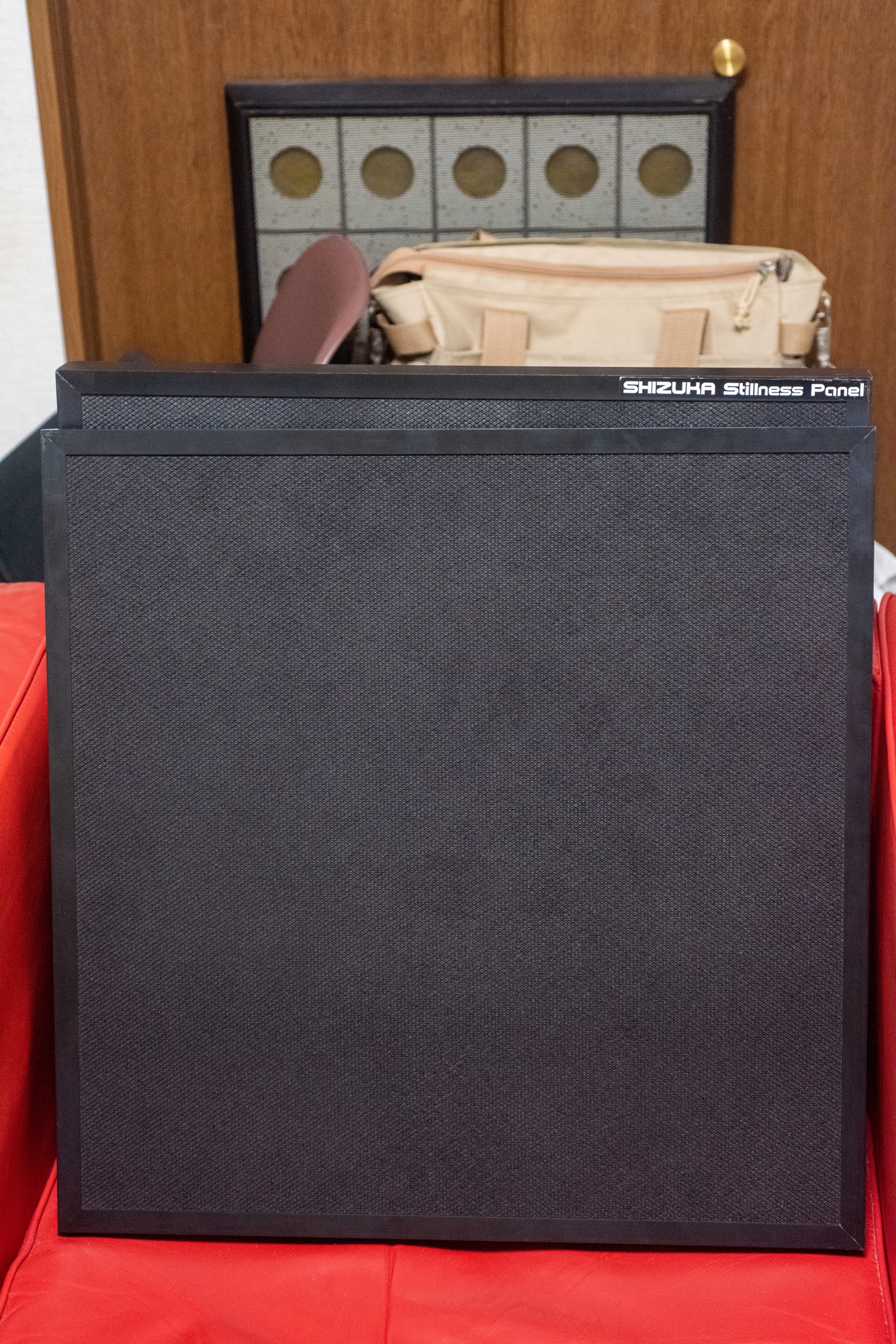 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio