 Audio
Audio Stetzer Electric STETZERiZERを追加
Stetzer Electricの電源フィルタ「STETZERiZER」をもうひとつ追加で導入してみました。すでにGreenwaveを2つ、STETZERiZERをひとつ使っていますが、2Pで気軽に挿せるSTETZERiZERが便利かなと。...
 Audio
Audio  Audio
Audio 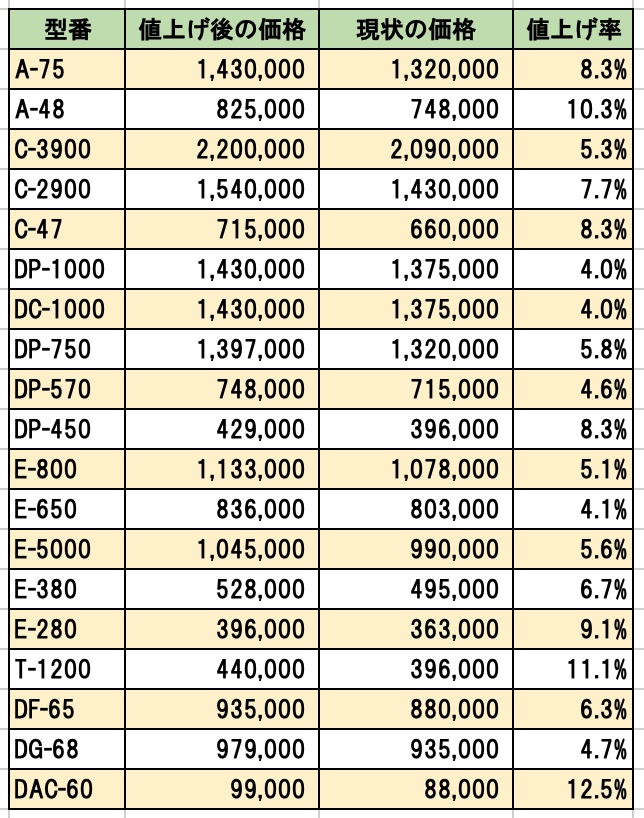 Audio
Audio 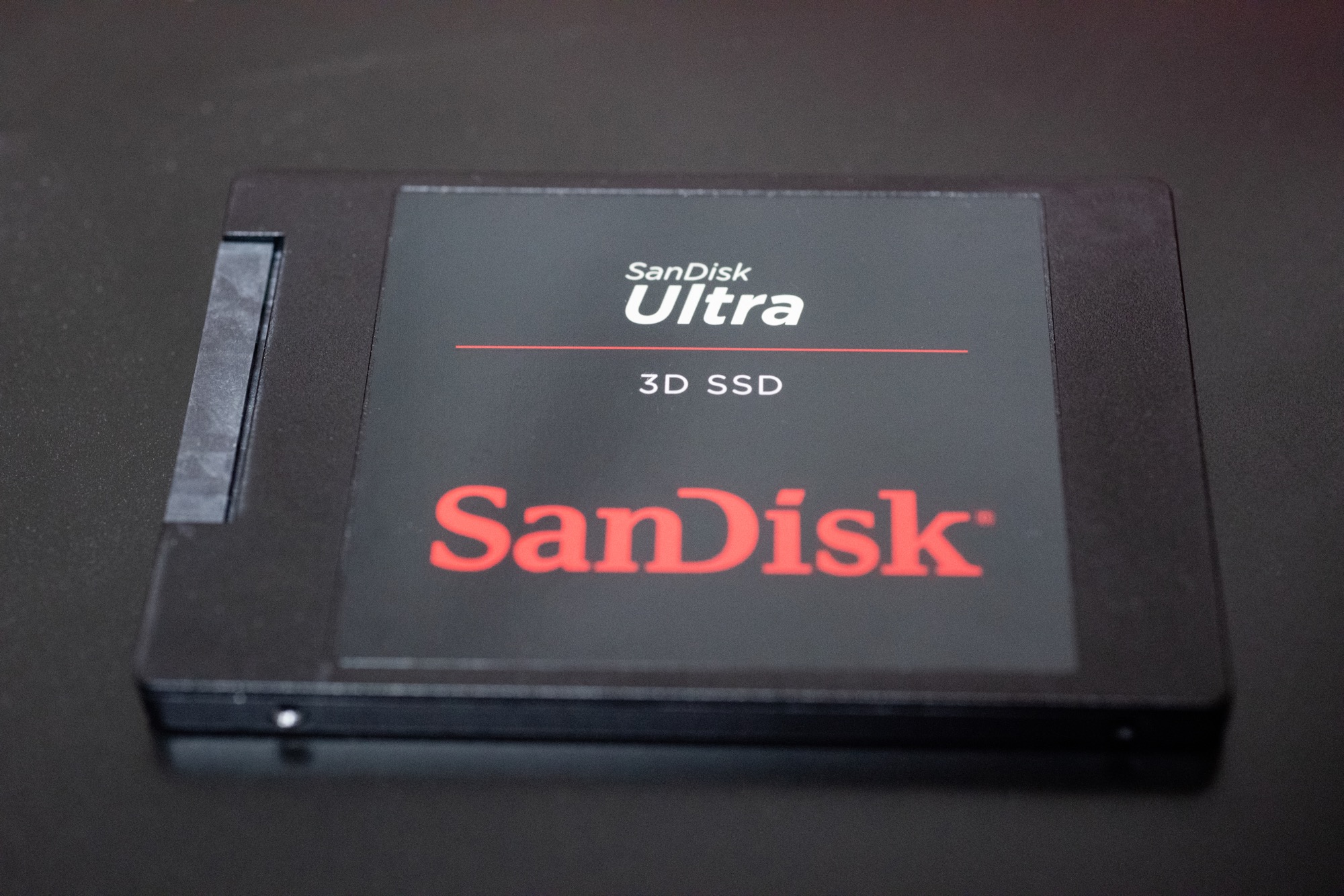 Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio  Audio
Audio