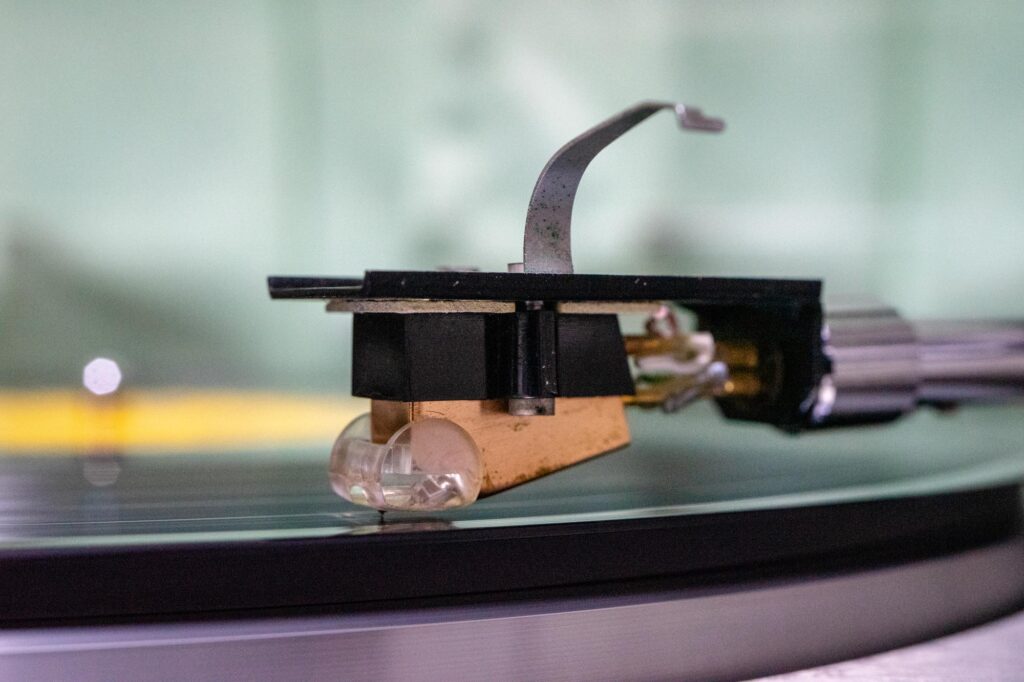 Audio
Audio Grace F-8L、再び
GraceのMMカートリッジ「F-8L」を再び入手しました。再びといっても前のも手放していないし、そもそもF-8をすでに3本持ってるので正確には今回のが4本目のゲットということになります。これまでのは当時の交換針でしたけど、今回のものはおそ...
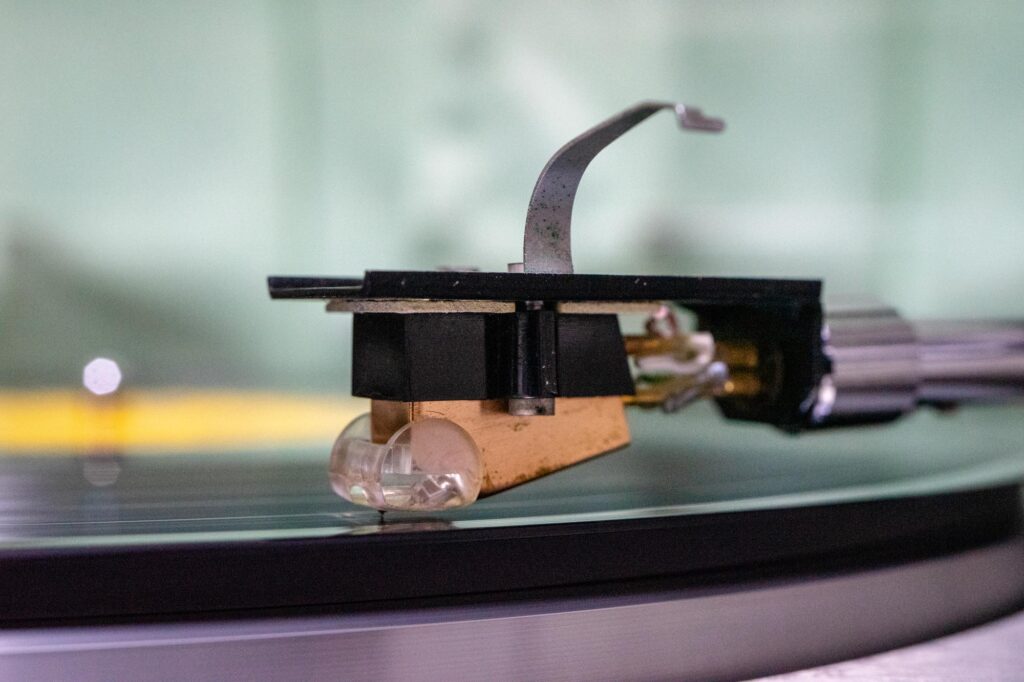 Audio
Audio  Audio
Audio 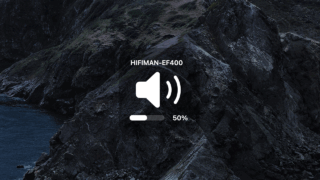 Mac
Mac  Audio
Audio  Electronics
Electronics  Audio
Audio  その他
その他 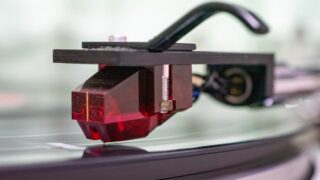 Audio
Audio  Audio
Audio 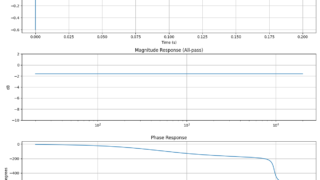 Audio
Audio