 PC
PC ELECOM XGM15BBBU
エレコムのBluetoothマウス「XGM15BBBU」を追加導入してみました。Surface Proのタッチパッドでもほとんどの操作は快適にできるのですが、ファイル操作とか細かい作業はやっぱりマウスでないと厳しい場面があったので必要かなと...
 PC
PC  PC
PC  PC
PC  PC
PC  PC
PC  PC
PC 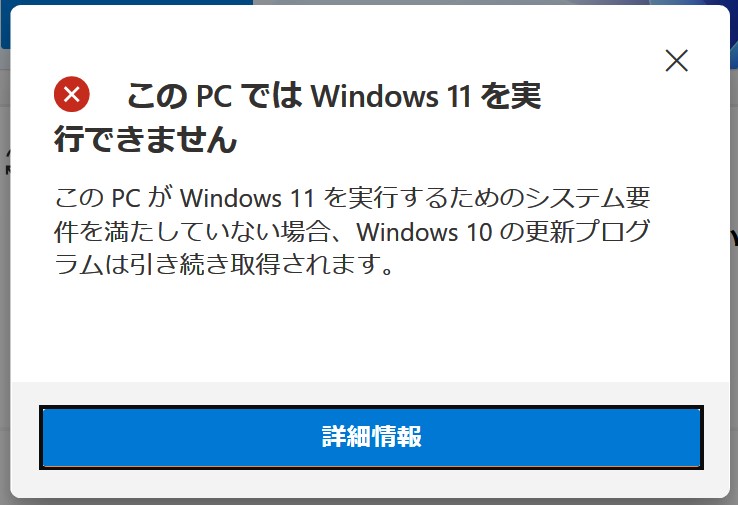 PC
PC  PC
PC  PC
PC  PC
PC